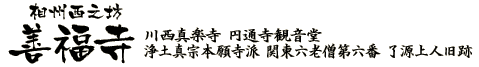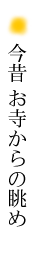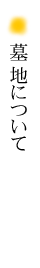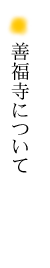後鳥羽院の寵を受けた朝廷の武官、藤原範茂と承久の乱
太上法皇(譲位により皇位を後継者に譲り、かつ出家した天皇)たる後白河法皇の院宣を受ける形で後鳥羽天皇が践祚したのは寿永二年(西暦1183年)、時に齢わずか3という、まだ幼き高御座の主の誕生でございました。世は源平合戦の直中、河内源氏の一族であります源義仲(木曾義仲)軍が京に迫り、平家一門が安徳天皇(高倉天皇の第一皇子。母は平清盛の娘、徳子)とともに西国へと逃れたことに起因した後鳥羽天皇の践祚によって、正史上初めて二人の帝が存在する事態を招いてしまうこととなったのでございました。
三種の神器なくしての即位から、事実上の重複在位など異例づくしの中、第八十二代天皇となった後鳥羽帝でしたが、建久三年(西暦1192年)の後白河院崩御までは院政が続き、その後は幼年の帝を擁して関白・九条兼実が事実上朝廷での実権を掌握、政治を主導するのでした。しかしながら故実先例に厳格で公事・作法の過失・懈怠に対して過状を求めたり勘責を加えたりする姿勢や、大納言は摂関家・花山院流・閑院流などの上流貴族にのみ許されるようにするなどの朝廷人事は中級・下級貴族らの反発を招くこととなり、建久七年の政変(建久七年・西暦1196年)で兼実は失脚、最後の望みでもあった娘である中宮・任子も皇子の誕生なく、政争の中内裏から退去させられるに至り、兼実の勢力は朝廷から一掃されてしまうこととなるのでございました。
政変後には、兼実に冷遇されていた善勝寺流や勧修寺流の貴族を味方に引き入れ、兼実追い落としの機を伺っておりました源通親が朝政の実権を握ることとなりました。兼実の権勢に翳りが見え始める中、自らの養女・在子が皇子(為仁、後の土御門天皇)を産んだことで一気に地歩を固めた通親でございましたが、建久九年(西暦1198年)には先例や幕府の反対を押し切る形で土御門天皇の践祚を強行、帝の外祖父として朝政を主導してゆくこととなるのでございます。土御門天皇への譲位により太上天皇となっておられました後鳥羽上皇でしたが、建仁二年(西暦1202年)通親が亡くなると、周りにはもはや後鳥羽上皇を諫止できる者がいなくなり、ここに後鳥羽院政が本格的に始まることとなるのでございました。
後白河院も既に崩御、建仁二年(西暦1202年)には失脚した前の関白九条兼実は出家し、源通親(土御門通親・正二位、追贈 従一位)は薨逝、また過ぐる建久十年(西暦1199年)には鎌倉の源頼朝も逝去しておりますことから、いよいよ名実共に治天の君として院政を布き、朝政を主導する後鳥羽院でございましたが、この時すでに、鎌倉を本拠とする坂東武士による鎌倉政権は、それまでの頼朝率いる鎌倉方による、武力を背景としつつも従来の権力者たちとは少し性質を異にする、新しい形での朝廷との交渉の末、幕府による統治機構に律令制における一定の公的側面を持たせることを成しえておりました。
さて、『新古今和歌集』を自ら撰するなど学芸に優れるだけではなく、狩猟を好み武芸にも通じるところのございました後鳥羽院は、『天下三不如意』で知られる白河法皇の御代に形作られたとされる、上皇の身辺警衛や御幸に供奉した武士であり、いわば院の直属軍としての性質を持っていた北面武士に加えて、新たに西面武士を設置し、軍事力の増強を図られたのでございました。北面武士と申しますれば、創設期の構成は近習や寵童といった院と個人的な関係の深い者が中心でございましたが、後に源氏平氏といった、それぞれがある程度の武士団を従えております、いわゆる軍事貴族が加わるようになり、名実共に院の直属軍としての性質を帯びたものとなってきたのでございます。平正盛(清盛祖父)、平忠盛(清盛父)、源義朝(頼朝、義経父)等もみな北面武士でございました。新たに設立された西面武士は、主に西日本の有力御家人から成っており、元々は院御所の北面(北側の部屋)の下に詰め所があった北面武士に対して、院御所の西面に詰め所などがあったことから、このように呼ばれるようになったそうでございます。共に院の軍事面を司る武士団であり、世の乱れが武士たちの力を必要とする中で、自らの地位もまた上げてゆかんとする者たちの集まりでございました。取り分け西面武士成立の背景には、やはりこの時期まだ西国に対する幕府の支配力も限られたものであり、未だ成立して間もない幕府と朝廷との、事実上の二元政治体制ゆえの混乱がございましたことは否めない理となりますでしょうか。
諸国に置かれた数多くの荘園が後鳥羽上皇の財源となっておりましたが、これらの荘園にも幕府補任の地頭が置かれはじめると、地頭に本来与えられた徴税権を超え、様々な理由をつけては荘園領主・国司への年貢を滞納、あるいは実質横領をする事態を招くことにつながり、しばしば荘園領主側との紛争へとつながってまいりました。
そのような中、承久元年(西暦1219年)一月、鎌倉幕府三代将軍である源実朝が甥の公暁に暗殺され、源氏将軍が断絶、それが故に生じた将軍継嗣問題では、最終的に幕府は皇族将軍を諦め、摂関家から将軍を迎え(後の九条頼経)新たに鎌倉殿とし執権が中心となって政務を執る執権体制へと移行していくことで落着いたしましたものの、朝廷方にも幕府方にも結果的にしこりをのこすものとなったのでございました。
朝廷と幕府との緊張は次第に高まりゆく中、土御門上皇はじめ摂政近衛家実、その父基通など多くの公卿たちが反対、または消極的姿勢を示すものの、後鳥羽上皇は幕府執権・北条義時を討つ意志を固めていくのでございました。そして承久三年(西暦1221年)後鳥羽上皇は「流鏑馬揃え」を名目として諸国の兵を集めるのでございます。北面・西面武士や近国の武士、大番役の在京の武士などあわせて1700余騎が集まったと伝えられておりますが、幕府出先機関たる京都守護の大江親広(大江広元の子)は朝廷方に応じ、同じく京都守護であった伊賀光季はその招聘を拒んだのでございました。朝廷方の藤原秀康、大内惟信勢が伊賀光季邸を襲撃、光季はわずかな兵で奮戦するも討死、時を同じくして後鳥羽上皇が三浦氏・小山氏・武田氏などの有力御家人に対して、北条義時追討の院宣を発しましたのは、承久三年(西暦1221年)の「流鏑馬揃え」翌日、五月十五日のことでございました。同日、朝廷からも諸国の御家人、守護および地頭らに対し広く義時追討の官宣旨が出され、北条義時はここに朝敵とされるにいたったのでございました。
国を治めるには如何にしても統治の仕組み、組織というものが必要となってまいります。長きにわたり朝廷を中心に政がおこなわれ、いつの時も権力者はその朝廷の中で力を得ること、朝政を実質主導する立場となることを目指すことで権力交代が行われてきた日ノ本では、国を治めるために必要な知見もまた朝廷に類聚されてまいりました。これまでにも、朝廷の支配が強く及ばない地において独自の統治体制が確立されてきたことはございましたものの、この鎌倉を中心とした幕府体制のように、朝廷の中心的支配地にまで影響を及ぼし得るような他の統治体制というものは、朝廷にとって嘗てない脅威であったことは想像に難くなく、北面武士や西面武士のように、朝廷の命に従う、あくまでも朝廷の武力としての存在たることを省察させる意で院より発せられた戒めの下達とも言えるものでございました。
事実上の幕政統括の身たる執権・北条義時に対し後鳥羽上皇より追討の院宣が発せられ、義時が朝敵とされましたことは、鎌倉の武士たちにやはり少なからぬ動揺を与えることとなりました。ここで御家人たちに対し、尼御台・尼将軍と呼ばれた北条政子が武士たちの今日の暮らしがあるは故・頼朝が武家による政の基を築いてきたからに外ならず、その恩顧を訴えて御家人たちの動揺を抑えてまとめたと伝えられております。尤も、このような世が大きな乱れを見せている中、御家人たちも皆一族の生き残りがかかっている時でございます。その様な折、如何に勝ち馬に乗るかを慎重に見定め、旗幟を鮮明にする動きはやはり多くの家において行われた様でございました。
鎌倉での戦評定においては、箱根、足柄にて迎え撃つという策が大方を占めるものでございましたが、幕府重鎮の大江広元は攻め上る策を進言、尼将軍政子の断により東海道、東山道、北陸道の三方から京へ向けて軍勢を進めたのでございました。その数『吾妻鏡』に号して19万の大軍とされております。ただ当時の状勢を鑑みましても、さすがにこの数は誇張が過ぎるものと考えざるを得ないところがございますものの、少なくとも鎌倉方は朝廷方を大きく凌駕する兵力で京へ向けて攻め上ったのでございました。
世に言う『承久の乱』、『承久の変』、『承久合戦』につきましては、細かな事の次第にいたるまで多くが語られておりますが、院宣を絶対視しておりました朝廷に対し、事実上朝廷に対して直接武力で立ち向かうという、それまでに類を見ない姿勢と、京に向けて攻め上ってくる鎌倉方の軍勢の姿とは、朝廷側をして狼狽させて余りあるものでございました。鎌倉幕府側の意向により後鳥羽上皇を含む三上皇が配流され、仲恭天皇も廃されるという史上類を見ない終幕をむかえることになるのでございますが、この折幕府の意向により多くの荘園、所領が召し上げられ、恩賞として鎌倉方の武士に与えられることとなり、鎌倉幕府が西国への支配力をも強めることへとつながるのでございました。
さて、この戦において、朝廷方の陣営には左衛門佐・左兵衛佐・左近衛少将と武官を歴任してまいりました公卿である藤原範茂がおりました。藤原不比等の嫡子たる藤原武智麻呂を祖とする藤原南家は、後に伊東氏・二階堂氏・相良氏といった武家の名族を輩出していくことでも知られておりますが、藤原範茂はその藤原南家に連なる南家高倉流の祖、藤原範季の次男でございました。後白河院の近臣として仕えた範季は、高倉天皇の第四皇子・尊成親王(後の後鳥羽天皇)の養育にあたり、また娘重子は女房として内裏に出仕、後鳥羽天皇の寵愛を受けて、建久八年(西暦1197年)には第二皇子・守成親王(後の順徳天皇)を産むこととなるのでございます。そのような流れもあり、藤原範茂は後鳥羽上皇の寵臣として仕え、また後鳥羽院と自身の姉・重子(修明門院)との子である順徳天皇の近臣でもあり、承久二年(西暦1220年)には従三位・参議に叙せられ公卿に列することとなったのでございます。
武官を歴任し、後鳥羽院の信任も厚かった範茂は、自らも幕府方と兵刃を交えるべく、宇治川の戦いに出陣いたしましたものの、鎌倉方には抗し得ず敗退、ほどなく六波羅(この時期には京都守護の庁舎が置かれておりました。)に拘禁された範茂は、幕府により乱の首謀者のひとりとして斬罪と定められてしまうのでございました。その後、都での処刑を避ける目的で東国へと護送される途上、斬首され首が胴から離れてしまい、五体に不具があっては往生に障りがあるから、と自ら入水を希望、着物のたもとやふところに石を入れ、足柄山の麓の清川の底に入水し最期を遂げたと伝えられております。
辞世の歌
思いきや 苔の下水 せきとめて
月ならぬ身のやどるべきとは
南足柄市怒田、善福寺のすぐ裏手には範茂史跡公園があり、室町時代前期の作で範茂の墓と伝えられる宝篋印塔がございます。



【関連サイトのご紹介】
範茂史跡公園
室町時代前期の作で範茂の墓と伝えられる宝篋印塔があります。